第23回ボイルドエッグズ新人賞
2020年2月3日
受賞の言葉
大島怜也
定職についたことがない。つこうと考えたことすらない。バイトも月百時間以上したことはほぼない。自分のことしか考えてない。嫌なこと面倒なことからはずっと逃げてきた。掛け値なしのクズだ。
「小説を書く」という護符がなかったら、もっとひどいことになっていただろう。そう考えるとぞっとする。
十年以上前のことだ。ある演劇専門学校の卒業公演に、助っ人のようなかたちで出演した。生徒のひとりに、芝居未経験のN君という青年がいた。彼はいまどきマンガにも出てこないような瓶底メガネをかけ、全身から物凄まじい負のオーラを放っていた。
いまもって、なぜ彼が人前に立って演技をやってみたいなどと考えたのか、皆目見当がつかない。セリフは棒読み、そもそもなにを言っているのか聞きとることすら困難で、動きは絶望的に硬かった。
が、そんなN君をぼくは「おもしろい」と感じていた。しかし彼は稽古が終わるといつも一目散に帰ってしまったから、対話の機会はもてずにいた。
結局、打ち上げではじめて、時間にしてわずかに五分程度話すことができた。話してみると案外ふつうの、ちょっと人づきあいが苦手なだけの若者だった。彼はぼくに、好きな作家と好きな芸人の名を教えてくれた。
「自分の小説を読ませてみたいな」深夜のカラオケボックスでそう思ったのをおぼえている。この無口で陰気な青年が、熱っぽく感想を伝えてくれたりしたら、きっとすごくうれしいだろうなと。
その思いがかなうことは、だがもう永久にない。数年後彼が死んでしまったからだ。真偽のほどは定かでないが、どうも自殺らしいとのことだった。
ぼくは薄情な人間だから、それ以上なにも聞かなかったし、泣きもしなかった。ただ、そのときもこう思っただけだ。ああ、彼に、小説を読んでもらいたかったな。
ぼくはクズだ。けれど、クズにはクズにしか書けないものがある。底からしか見えない景色がある。またいつかN君みたいな、笑っちゃうくらい生きづらさを丸だしにした青年と出会うことがあったら、こんどは無理にでも自分の小説を読ませてやろうと思う。
それで彼だか彼女だかが「こんなダメなひとでも、自信満々で生きてられるんですね」そう言って笑ってくれでもしたら、いかな不人情のぼくといえど泣いてしまうかもしれぬ。
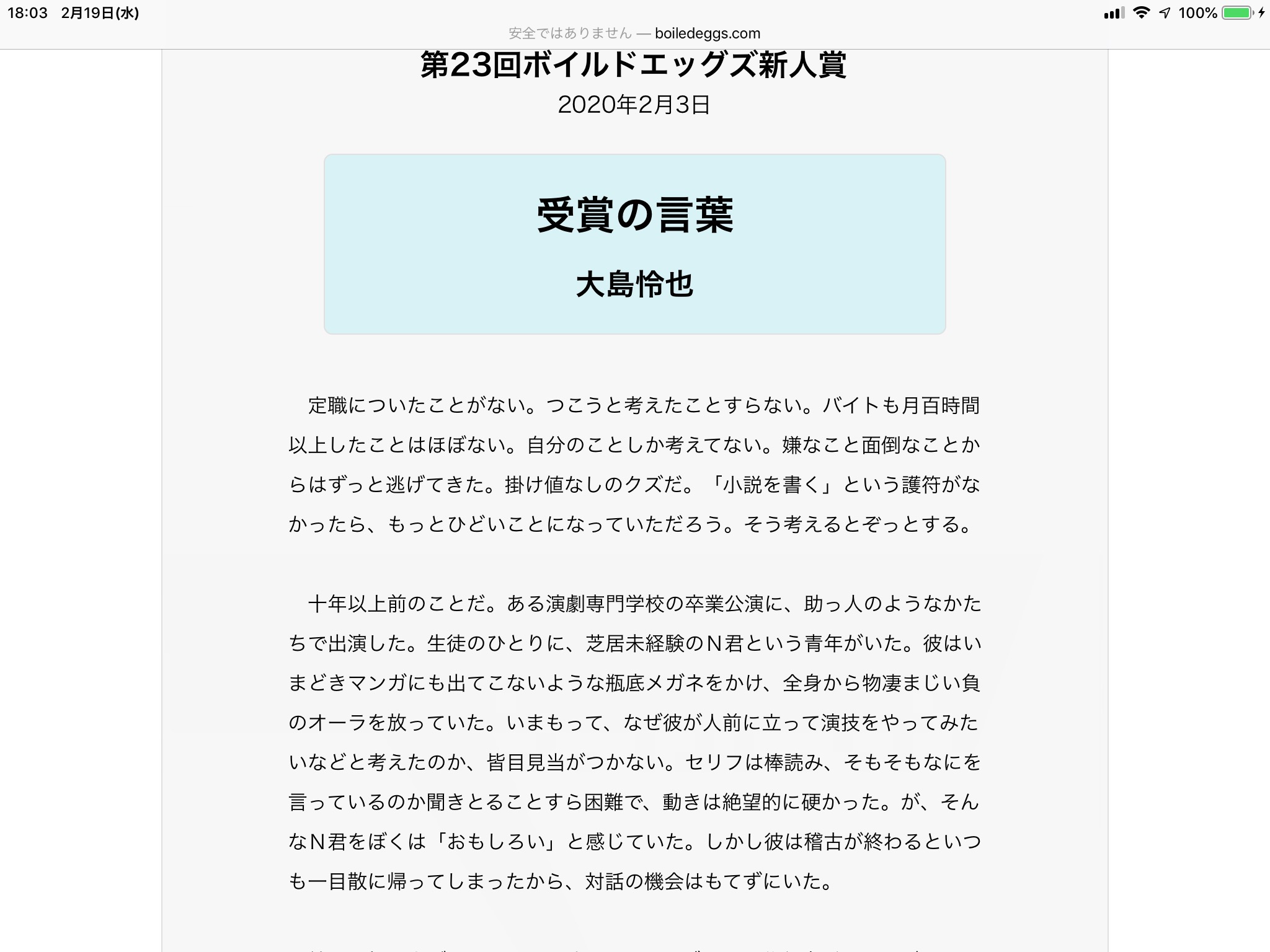


コメント
最新を表示する
NG表示方式
NGID一覧